三重県伊賀市 本尊五大明王の祈願寺
今年の干支は、甲午(きのえうま)
「午」とは、皆さまよくご存じ馬のことです。
先史時代の倭国に馬はおらず、大陸から伝来した文化と聞きます。
食用・毛皮といった単なる家畜の用途に留まらず、乗馬・運搬・農耕・軍用などさまざまに活用され、紀元前より人類の歴史は、まさに馬と共に歩んできました。
現在では、牧場や競馬、特別な神事などでお目に掛る程度ですが、今なお多くの人々に愛し親しまれる特別な動物であります。
仏教においても馬は、瘤(こぶ)牛・象・獅子といったインドの四聖獣として取り入れられています。
最たるものは、馬の頭を頂く馬頭観音(ばとうかんのん)でしょう。ちょうど、私が住職を勤める上郡の蓮勝寺が、この仏を本尊に仰いでいます。
馬頭観音(hayagriva)は、観世音菩薩の変化仏の一つ。ヒンドゥー教の最高神ヴィシュヌの異名でもあります。
女性的で穏やかな表情をされている観世音菩薩の変化仏において、例外的に、目尻を吊り上げ、怒髪天を衝き牙を剥く忿怒(ふんぬ)相であることから「馬頭明王」と、明王部の一尊として数えられる場合もあります。
宝馬が力強く野を駆ける、その威勢が諸悪を打ち祓う。大食の馬が草を食むように、衆生の無明悪障を全て食らい尽くす馬頭観音。
その姿形から、馬の守護仏。さらには、あらゆる畜生道を化益する仏として民間に信仰されています。
蓮勝寺の馬頭観音像は、不幸にも昭和五十九年の火災により堂宇と共に消失。今の本尊は、新たに造り直されたものです。
この馬頭像の造立には、不思議な逸話が伝わっています。
蓮勝寺の火難から、少し後、名張市薦生(こも) 明王院のご老僧 岡田快浄(かいじょう)師の夢枕に馬頭観音さまが現れ、新しい馬頭尊像を彫って欲しいと告げられたそうです。
快浄師はこの天啓を受け、楠の霊木から愛らしい童子の姿の馬頭観音像を一体彫刻。本堂再建に併せて、その像をご寄進くださいました。
本堂再建より、間もなく30年。今日も、愛らしい童子姿の馬頭観音が、皆さまの暮らしを見守っておられます。干支に因んだ、馬頭の仏さま。ぜひ一度お参りになられてください。
暁の 夢路に告げし 馬頭尊
衆生の厄を 食みて護らん
※ 依那古仏教団の教化誌 『法縁』 第89号に寄稿したものを加筆修正しました。
PR
新年明けましてお目出とうございます。
除夜の鐘を打ちながら去りゆく一年を思い、初日の出に新たな願いを託し、新しい年、新しい今日を迎えることが出来ましたこと、皆さまと共にうれしく存じます。
中国に『日に新たに、日々に新たに、又日に新たなり』という言葉があります。
これは、中国の聖人と言われる、殷(いん)王朝の創始者「湯王(とうおう)」が戒めの辞として洗面器に刻み、毎日洗顔の度に繰り返し読み、自身の体の垢をこすって落とすように、心も洗い清めて、新しい自分を磨かんと、自身に言い聞かせ心の糧として修養したといわれております。
それによって大成し、民衆より信望される明君になったと有ります。
皆さまも、心の支えとなっている言葉や教えを改めて思い、一年の計と共に再考されてはいかがでしょうか。
ところで、文化は急速に進んでおりますが、公害や異常気象に起因すると思われる台風や、今まで経験のない豪雨災害に、又知らぬ間に進んでいる自然破壊や、逃れられない天変地異等による苦しみが次々現れています。どうすれば良いのでしょうか。
こんな時機こそ私たちは、人が本来備えている「ほとけの心」を見い出し、心穏やかに過ごすための大切な智恵が必要と思われます。
「ほとけの心」とは慈悲、即ち慈しみを持つ心・哀れみを持つ心であり、それに気付き得ん為に、思慮深く実践行に勤めたとき、苦しみ・悩みを解決する糸口をきっと見つけることが出来、迷いは晴れると確信します。
この智恵を頂いて、先徳の御諭しを教訓に精進し、み仏のご加護を頂き、与えられたこの命を悔いなく全うして頂きたいと思います。
今年こそ、平穏な一年でありますよう祈念致します。
常福寺住職 織田杲深 執筆
※ 常福寺 正月寺報より転載
5月の某日、歩き遍路でお参りしたお寺の本堂に、大きな百足(ムカデ)の額が掲げられていました。

(伊賀四国 第7番 妙覚寺(鍛冶屋)に掲げられた”ムカデ”の額)
予想通り、檀信徒のお一人から質問が。
「和光さん、なんでムカデの額が掛けてあるんですか?」
「あぁ、それはね。ムカデが、このお寺の本尊 毘沙門天さまの眷族(けんぞく)だからなんです」
「……眷族って何ですか??」
そうか、しまった…!? 眷族って、一般用語じゃあなかったか~(汗)
常々、檀信徒の皆さまにお話しする際は、専門用語だけで済ませない、用いる時には必ずその簡単な説明や例えを加えるように心掛けているのですが、今回は失敗…。慌てて補足しました。
眷族とは、「親眷愛族」の略語。
狭義では、血縁の者や一族郎党。広義では、侍者や従者、部下や家来、取り巻きの者を指す言葉です。仏教では、薬師如来を守る十二神将や、不動明王に従う八大童子などが有名です。
「…つまり、助さん格さんは、水戸黄門さまの眷族ってことになりますね~笑」
補足説明によって、どうやらご理解いただけた様子。
実は、にょろにょろと細長い生き物は、みな何かしら仏さまの眷族なのです。
例えば、“蛇”は弁天さまや数多の龍神の眷属。“うなぎ”は、虚空蔵菩薩の眷属。そして“ムカデ”は、毘沙門天の眷属と、私たちの暮らしの身近にいるにょろにょろした細長い生き物は、大体が何かしら仏さまの眷属になっているようです。
…それじゃあ“みみず”だって、きっとどなたかの眷属に違いない!!と、常々思っていたのですが、最近その答えを耳にする機会を得ました。
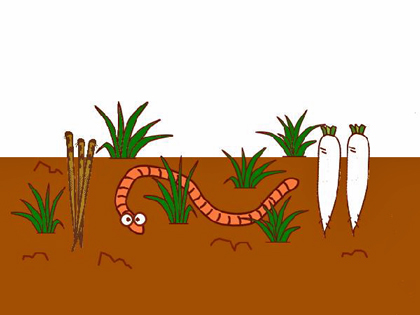
“みみず”を漢字で書くと「蚯蚓」ですが、漢方薬などに用いられる際は「地龍」という名で呼ばれるそうです。
なるほど、みみず は土に含まれる微生物や有機物を食べ、排泄することで土壌を豊かにする益虫です。小さいながらも、地中を這う立派な龍の眷属という訳ですね…。
長年の疑問が一つ説けて、すっきりした心地になりました。
(伊賀四国 第7番 妙覚寺(鍛冶屋)に掲げられた”ムカデ”の額)
予想通り、檀信徒のお一人から質問が。
「和光さん、なんでムカデの額が掛けてあるんですか?」
「あぁ、それはね。ムカデが、このお寺の本尊 毘沙門天さまの眷族(けんぞく)だからなんです」
「……眷族って何ですか??」
そうか、しまった…!? 眷族って、一般用語じゃあなかったか~(汗)
常々、檀信徒の皆さまにお話しする際は、専門用語だけで済ませない、用いる時には必ずその簡単な説明や例えを加えるように心掛けているのですが、今回は失敗…。慌てて補足しました。
眷族とは、「親眷愛族」の略語。
狭義では、血縁の者や一族郎党。広義では、侍者や従者、部下や家来、取り巻きの者を指す言葉です。仏教では、薬師如来を守る十二神将や、不動明王に従う八大童子などが有名です。
「…つまり、助さん格さんは、水戸黄門さまの眷族ってことになりますね~笑」
補足説明によって、どうやらご理解いただけた様子。
実は、にょろにょろと細長い生き物は、みな何かしら仏さまの眷族なのです。
例えば、“蛇”は弁天さまや数多の龍神の眷属。“うなぎ”は、虚空蔵菩薩の眷属。そして“ムカデ”は、毘沙門天の眷属と、私たちの暮らしの身近にいるにょろにょろした細長い生き物は、大体が何かしら仏さまの眷属になっているようです。
…それじゃあ“みみず”だって、きっとどなたかの眷属に違いない!!と、常々思っていたのですが、最近その答えを耳にする機会を得ました。
“みみず”を漢字で書くと「蚯蚓」ですが、漢方薬などに用いられる際は「地龍」という名で呼ばれるそうです。
なるほど、みみず は土に含まれる微生物や有機物を食べ、排泄することで土壌を豊かにする益虫です。小さいながらも、地中を這う立派な龍の眷属という訳ですね…。
長年の疑問が一つ説けて、すっきりした心地になりました。
謹賀新年。皆さま、本年も宜しくお願い申し上げます。
今年の干支は、癸巳(みずのとみ) 巳とは、にょろにょろ細長い蛇のことです。その地を這う姿やイメージから、蛇が大嫌いだという方も多いことでしょう。でも、ちょっと考えてみてください。蛇って、本当に皆に嫌われるだけの存在でしょうか。

(アダムとイヴの楽園追放)
旧約聖書の『創世記(そうせいき)』有名なアダムとイヴの神話に登場する蛇は、イヴを唆(そそのか)して禁断の果実を齧(かじ)らせます。
結果、二人はエデンの園を追われ(失楽園)以来、蛇は地を這い忌み嫌われる存在となりました。キリスト教では、件の蛇を悪魔そのものと説くそうです。これは、完全に悪役ですね。
しかし、日本を始めアジア各国では、蛇は神秘的な存在として、神の使いや神そのものとして扱われることが多くあります。
仏教では、弁財天やあまたの龍神、軍荼利(ぐんだり)明王など。神道でも、例えば奈良の大神(おおみわ)神社や天河神社など、蛇そのものを神仏化してお祀りしている社寺は、全国で枚挙に暇がありません。
それに昔から多くの日本人は、毎年正月になると、蛇の姿を模したものを家の隅々まで大切にお飾りしているのです。
答えが解りますか? 正解は…、鏡餅や注連縄(しめなわ)です。形を思い出してください。鏡餅は、蛇がとぐろを巻いている姿。注連縄は、雌雄の蛇が交合している姿。言われてみれば、そのものズバリでしょう。

実は、日本を始め多くのアジア各国は、古来より潜在的に蛇を信仰してきた民族(スネークカルト)なのです。一説によると、縄文式土器に入っている縄目の模様も、同じく雌雄の蛇の姿だとか…。符号が合いすぎて、否定する方が難しい気がします。

(広葉杉に注連縄のお飾り)
巳年の正月ですので、蛇が大嫌いな方にもちょっと視点を変えるようなお話をさせて頂きました。
あんな姿をしていますが、そんなに悪い存在でもないのですよ。あまり嫌わないであげてくださいね。
※ 依那古仏教団の教化誌『法縁』第88号に寄稿したものを加筆修正しました。
今年の干支は、癸巳(みずのとみ) 巳とは、にょろにょろ細長い蛇のことです。その地を這う姿やイメージから、蛇が大嫌いだという方も多いことでしょう。でも、ちょっと考えてみてください。蛇って、本当に皆に嫌われるだけの存在でしょうか。
(アダムとイヴの楽園追放)
旧約聖書の『創世記(そうせいき)』有名なアダムとイヴの神話に登場する蛇は、イヴを唆(そそのか)して禁断の果実を齧(かじ)らせます。
結果、二人はエデンの園を追われ(失楽園)以来、蛇は地を這い忌み嫌われる存在となりました。キリスト教では、件の蛇を悪魔そのものと説くそうです。これは、完全に悪役ですね。
しかし、日本を始めアジア各国では、蛇は神秘的な存在として、神の使いや神そのものとして扱われることが多くあります。
仏教では、弁財天やあまたの龍神、軍荼利(ぐんだり)明王など。神道でも、例えば奈良の大神(おおみわ)神社や天河神社など、蛇そのものを神仏化してお祀りしている社寺は、全国で枚挙に暇がありません。
それに昔から多くの日本人は、毎年正月になると、蛇の姿を模したものを家の隅々まで大切にお飾りしているのです。
答えが解りますか? 正解は…、鏡餅や注連縄(しめなわ)です。形を思い出してください。鏡餅は、蛇がとぐろを巻いている姿。注連縄は、雌雄の蛇が交合している姿。言われてみれば、そのものズバリでしょう。
実は、日本を始め多くのアジア各国は、古来より潜在的に蛇を信仰してきた民族(スネークカルト)なのです。一説によると、縄文式土器に入っている縄目の模様も、同じく雌雄の蛇の姿だとか…。符号が合いすぎて、否定する方が難しい気がします。
(広葉杉に注連縄のお飾り)
巳年の正月ですので、蛇が大嫌いな方にもちょっと視点を変えるようなお話をさせて頂きました。
あんな姿をしていますが、そんなに悪い存在でもないのですよ。あまり嫌わないであげてくださいね。
※ 依那古仏教団の教化誌『法縁』第88号に寄稿したものを加筆修正しました。
前から思っていたことですが…、
科学って不思議ですね。言うことがコロコロ変わる。
例えば、“昔は運動するときに「水を飲んではいけない」と言われたのに、今では水分補給を欠かしてはいけない”と言われる。“「水金地火木土天海冥」と憶えた太陽系の惑星の配列が、現在は「・・・冥海」で、果てはそもそも冥王星は惑星ではなかった”とか、“ニュートリノは光速を超えた、いや超えていない”などなど…。この他にも、さまざまな事柄(常識)が科学によって日々移ろい変わっているのです。
科学によって、今日の正論が明日には平気で覆される。数時間後には、また別の常識が生まれている。しかも、そんな移ろい変化している事柄を、誰もが文句ひとつ言わずに受容している…。
もちろん、科学が「現時点の水準で知りえた知識であって、常に新しい情報に更新されている」ことは存じ上げています。しかし、専門的な知識の乏しさもあるのでしょうが、どうも私たちは科学を素直に(強く)信じてしまう。私はそこに、科学に対する絶対なまでの信仰(盲信)を感じてしまいます。
いわば私たちは、科学という教えを篤く信仰しているのです。
片や、宗教はどうでしょう。
例えば仏教であれば、“思い通りにならない苦しみを受け入れて、与えられた人生を全うする”とか“親や兄弟、周囲の方々に感謝して、他人の為に行動をおこす”“実践のない思いに意味はない”など、さまざまな教えの中に、ブレは全く存在しない。今も昔も変化することなく、同じ教えを説き続けているのです。
しかし、そこに対する人々の信仰はどうでしょう。
これは、私たち宗教者に責任があるのかもしれませんが、私たち宗教者が説くほとけの(神の)教えは、一部の信仰心が篤い方々には素直に受け止められても、家庭的な環境や境遇など、素地のない(信心のない)人々には理解されない、全く相手にされないことはままあります。
科学のように、(盲信に近い)絶対の信頼とは対比することさえ可笑しい、雲泥の差を感じてしまいます。
昨年3月の東日本大震災によって、福島原発が事故を起こし、周辺に住む方々は住まいを追われ、今後数十年に渡り人が住めなくなるという、受け入れ難い悲惨な状況となりました。事態はさらに深刻で、撒き散らされた大量の放射性物質は国内に収まらず、地球規模の汚染被害をもたらしています。
専門の科学者が説く「安全」を鵜呑みに(盲信)した結果、大地震・津波がきっかけとなり取り返しのつかない人災を呼び起こしました。そして現在も、科学者による「安全」「危険」という言葉に振り回されて、国さえも右往左往している状態です。
例えが少し極端かもしれませんが、これもその一例。常々、私は感じています。
常に変化しブレ続ける「科学」と、決してブレずに真理を説き続ける「宗教」
果たして、どちらが信頼に足るものなのでしょうか?
科学って不思議ですね。言うことがコロコロ変わる。
例えば、“昔は運動するときに「水を飲んではいけない」と言われたのに、今では水分補給を欠かしてはいけない”と言われる。“「水金地火木土天海冥」と憶えた太陽系の惑星の配列が、現在は「・・・冥海」で、果てはそもそも冥王星は惑星ではなかった”とか、“ニュートリノは光速を超えた、いや超えていない”などなど…。この他にも、さまざまな事柄(常識)が科学によって日々移ろい変わっているのです。
科学によって、今日の正論が明日には平気で覆される。数時間後には、また別の常識が生まれている。しかも、そんな移ろい変化している事柄を、誰もが文句ひとつ言わずに受容している…。
もちろん、科学が「現時点の水準で知りえた知識であって、常に新しい情報に更新されている」ことは存じ上げています。しかし、専門的な知識の乏しさもあるのでしょうが、どうも私たちは科学を素直に(強く)信じてしまう。私はそこに、科学に対する絶対なまでの信仰(盲信)を感じてしまいます。
いわば私たちは、科学という教えを篤く信仰しているのです。
片や、宗教はどうでしょう。
例えば仏教であれば、“思い通りにならない苦しみを受け入れて、与えられた人生を全うする”とか“親や兄弟、周囲の方々に感謝して、他人の為に行動をおこす”“実践のない思いに意味はない”など、さまざまな教えの中に、ブレは全く存在しない。今も昔も変化することなく、同じ教えを説き続けているのです。
しかし、そこに対する人々の信仰はどうでしょう。
これは、私たち宗教者に責任があるのかもしれませんが、私たち宗教者が説くほとけの(神の)教えは、一部の信仰心が篤い方々には素直に受け止められても、家庭的な環境や境遇など、素地のない(信心のない)人々には理解されない、全く相手にされないことはままあります。
科学のように、(盲信に近い)絶対の信頼とは対比することさえ可笑しい、雲泥の差を感じてしまいます。
昨年3月の東日本大震災によって、福島原発が事故を起こし、周辺に住む方々は住まいを追われ、今後数十年に渡り人が住めなくなるという、受け入れ難い悲惨な状況となりました。事態はさらに深刻で、撒き散らされた大量の放射性物質は国内に収まらず、地球規模の汚染被害をもたらしています。
専門の科学者が説く「安全」を鵜呑みに(盲信)した結果、大地震・津波がきっかけとなり取り返しのつかない人災を呼び起こしました。そして現在も、科学者による「安全」「危険」という言葉に振り回されて、国さえも右往左往している状態です。
例えが少し極端かもしれませんが、これもその一例。常々、私は感じています。
常に変化しブレ続ける「科学」と、決してブレずに真理を説き続ける「宗教」
果たして、どちらが信頼に足るものなのでしょうか?
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
最新記事
(01/15)
(01/08)
(01/31)
(01/20)
(01/15)
ブログ内検索
プロフィール
HN:
和光さん
HP:
性別:
男性
職業:
副住職
趣味:
読書、息子と遊ぶこと
自己紹介:
真言宗豊山派のお坊さん
大和国は豊山長谷寺の門前町に生を受け、仏縁あって僧侶に。
伊賀国は江寄山常福寺の副住職になりました。
現在檀務と共に、ご詠歌、声明ライブ、豊山仏青、歩き遍路など、色々活動しております。
真言宗豊山派のお坊さん
大和国は豊山長谷寺の門前町に生を受け、仏縁あって僧侶に。
伊賀国は江寄山常福寺の副住職になりました。
現在檀務と共に、ご詠歌、声明ライブ、豊山仏青、歩き遍路など、色々活動しております。
カウンター
最新TB
アーカイブ
忍者アナライズ

