三重県伊賀市 本尊五大明王の祈願寺
昨年、好評を博した霊場会主催の「歩き遍路」が、今年も春から実施されています。開白法要のすぐ後から始まり、全15回で満願となる予定。すでに、5回目の行程まで終了しました。
 個人的には、下見から数えて3週目となる歩き遍路。極力参加することを心がけ、出仕回数は4/5。愛知のチャリティコンサートに出仕する為、一度だけ欠席しましたが、現在のところ成績は優秀なようです。
個人的には、下見から数えて3週目となる歩き遍路。極力参加することを心がけ、出仕回数は4/5。愛知のチャリティコンサートに出仕する為、一度だけ欠席しましたが、現在のところ成績は優秀なようです。
不思議なものですね。参加できないルートは、3年続けて何か予定が入ったりする。個人的に参拝したいお寺・拝観したい仏像などあるのですが、ご縁がないのでしょうか。残念でなりません。
さて今年度からは、参加人数が増えたこともあり、「歩き遍路」のよりよい実施方法が模索されています。その一つが、上野・名張と2班への分割。人数を分けることにより参拝・休憩時間を減らす狙いがあるのですが、同時にスタッフの数も多く必要になります。
特に、先導・準備・会計などは誰でもよい役ではなく、スタッフの確保は、担当されている観音寺さんがいつも頭を悩ませてくれているところです。
分割体制のため、最近は上野組・名張組が顔を合わさない日が続いたのですが、近日実施された第5回は、珍しく合流して一緒に歩くことに…。
久々にお会いする異なる組の方々。おひさしぶり、元気だった?と、交わす言葉に咲く笑顔。和気藹々と、にこやかな遍路一行が歩を進めました。
 やはり歩き遍路はいいですね! 檀信徒の皆さんと交流しながら、心身共に健康になれる気がします。
やはり歩き遍路はいいですね! 檀信徒の皆さんと交流しながら、心身共に健康になれる気がします。
得難い日常に感謝する気持ちを忘れずに、遍路修行を続けたいと思います。
写真:第5回 喰代~比自岐ルート の様子です。
当日の様子を詳しく知りたい方は…、伊賀四国霊場ブログ
ちなみに、第5回は私が執筆しました。
不思議なものですね。参加できないルートは、3年続けて何か予定が入ったりする。個人的に参拝したいお寺・拝観したい仏像などあるのですが、ご縁がないのでしょうか。残念でなりません。
さて今年度からは、参加人数が増えたこともあり、「歩き遍路」のよりよい実施方法が模索されています。その一つが、上野・名張と2班への分割。人数を分けることにより参拝・休憩時間を減らす狙いがあるのですが、同時にスタッフの数も多く必要になります。
特に、先導・準備・会計などは誰でもよい役ではなく、スタッフの確保は、担当されている観音寺さんがいつも頭を悩ませてくれているところです。
分割体制のため、最近は上野組・名張組が顔を合わさない日が続いたのですが、近日実施された第5回は、珍しく合流して一緒に歩くことに…。
久々にお会いする異なる組の方々。おひさしぶり、元気だった?と、交わす言葉に咲く笑顔。和気藹々と、にこやかな遍路一行が歩を進めました。
得難い日常に感謝する気持ちを忘れずに、遍路修行を続けたいと思います。
写真:第5回 喰代~比自岐ルート の様子です。
当日の様子を詳しく知りたい方は…、伊賀四国霊場ブログ
ちなみに、第5回は私が執筆しました。
PR
なんだか最近、托鉢のことばかり更新していますが…。先に記したのは、仏教青年会の托鉢について。今回は、伊賀四国霊場会の活動です。
伊賀四国霊場会も、やはり被災者支援のために出来ることをしようと、開白法要の後も、記念事業実行委員会が主軸となって托鉢を行っています。
まず実施したのは、4月23日(土)と、5月8日(日)。出来る限り協力したいと思っていましたが、三重仏青の托鉢と日程が重なり8日だけ参加。やはり、どのお坊さんも予定はほぼ同じ。たまたま空いていた同じ日が設定された次第です。
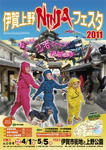 今、忍者の里・伊賀では、NINJAフェスタというお祭りが開催されていて、週末や祝日になると、忍者装束に身を包んだ子供たちが伊賀の町を闊歩しています。
今、忍者の里・伊賀では、NINJAフェスタというお祭りが開催されていて、週末や祝日になると、忍者装束に身を包んだ子供たちが伊賀の町を闊歩しています。
地元の方には自然な風景でも、初めての方には驚きの風景。近年では、NINJAが大好きな外国人観光客にも好評で、来訪者数も年々伸びているそうです。
ちょうど、取材を受けたネットTVの動画をリンクしておきます。私が行けなかった23日の映像で、霊場会会長としてうちの住職がインタビューに答えています。雨天のため観光客もまばらですが、托鉢の様子が少しでも伝われば幸いです。
動画で「托鉢」の様子を見たい方は…、コチラ
伊賀タウン情報YOU ネットTVにて紹介されました。
伊賀四国霊場会も、やはり被災者支援のために出来ることをしようと、開白法要の後も、記念事業実行委員会が主軸となって托鉢を行っています。
まず実施したのは、4月23日(土)と、5月8日(日)。出来る限り協力したいと思っていましたが、三重仏青の托鉢と日程が重なり8日だけ参加。やはり、どのお坊さんも予定はほぼ同じ。たまたま空いていた同じ日が設定された次第です。
地元の方には自然な風景でも、初めての方には驚きの風景。近年では、NINJAが大好きな外国人観光客にも好評で、来訪者数も年々伸びているそうです。
ちょうど、取材を受けたネットTVの動画をリンクしておきます。私が行けなかった23日の映像で、霊場会会長としてうちの住職がインタビューに答えています。雨天のため観光客もまばらですが、托鉢の様子が少しでも伝われば幸いです。
動画で「托鉢」の様子を見たい方は…、コチラ
伊賀タウン情報YOU ネットTVにて紹介されました。
開白法要から一月が経ちました。遅ればせながら、再びこぼれ話を紹介します。
 開白法要にて、常福寺世話役の方々が着ておられた揃いの法被(はっぴ)。実は、今回の法要に合わせて新調したものです。
開白法要にて、常福寺世話役の方々が着ておられた揃いの法被(はっぴ)。実は、今回の法要に合わせて新調したものです。
法被とは、日本の伝統装束で、お祭りの際や職人さん達がよく着られます。元々は武家の装束で、それを職人や町火消しが真似て着用するようになったようですね。半纏とは似て非なるものですが、江戸末期にはすでに混同されたようです。
実は私は、数年前から常福寺の揃いの法被を作りたかったのです。この開白法要を好機と住職に提案してみたら、「それはいい」とOKのお言葉。納期まで一月ほどしかありませんでしたが、業者の方と相談して制作に入りました。
 さてデザイン校正。背中に入るのは、常福寺の寺紋「五大」。漢数字の「大」が5つ、お花のように配置されたデザインです。常福寺本尊「五大明王」を表す古くからある紋で、これはすぐに決まりました。
さてデザイン校正。背中に入るのは、常福寺の寺紋「五大」。漢数字の「大」が5つ、お花のように配置されたデザインです。常福寺本尊「五大明王」を表す古くからある紋で、これはすぐに決まりました。
少し意匠を凝らしたのは、腰帯の部分。ここには、不動明王が左手に持されている「索」をイメージした柄を入れました。不動明王の索は、「あらゆる衆生を引き寄せ、正道に導くこと」を意味します。私たちや檀信徒を正しい道に導いてくださる。法被を着るのは、当然檀信徒の代表である方々ですから、とても相応しい意匠になりました。
あとは、生地の色。これは私のこだわりで、これまでお寺のホームページやチラシなどに、極力暖色を使うようにしてきました。言葉で色々イメージを伝えましたが、最終的には業者と職人さん任せ。納品されたものを見て、素晴らしい色合いに会心の笑みがこぼれました。
お蔭さまで、新調した法被は大好評!! よく映える色合いで、着て貰った世話役さんにも、お寺さん方にもお褒めの言葉をたくさん頂きました。これからは、寺行事で総代さん方に被着して頂くことになります。
尚、今回の制作に当り、鈴木法衣店の登丸さんに多大なご協力を頂きました。お蔭さまで、素晴らしい法被が出来上がりました。この場をお借りして、篤く御礼申し上げます。
写真1: 門前で集合写真
法被を着ているのが、世話役の方々。礼服の方は、総代OBです。
写真2: 法被の後姿
金棒役を後から撮影。お顔も紹介したかったのですが、あしからず…。
法被とは、日本の伝統装束で、お祭りの際や職人さん達がよく着られます。元々は武家の装束で、それを職人や町火消しが真似て着用するようになったようですね。半纏とは似て非なるものですが、江戸末期にはすでに混同されたようです。
実は私は、数年前から常福寺の揃いの法被を作りたかったのです。この開白法要を好機と住職に提案してみたら、「それはいい」とOKのお言葉。納期まで一月ほどしかありませんでしたが、業者の方と相談して制作に入りました。
少し意匠を凝らしたのは、腰帯の部分。ここには、不動明王が左手に持されている「索」をイメージした柄を入れました。不動明王の索は、「あらゆる衆生を引き寄せ、正道に導くこと」を意味します。私たちや檀信徒を正しい道に導いてくださる。法被を着るのは、当然檀信徒の代表である方々ですから、とても相応しい意匠になりました。
あとは、生地の色。これは私のこだわりで、これまでお寺のホームページやチラシなどに、極力暖色を使うようにしてきました。言葉で色々イメージを伝えましたが、最終的には業者と職人さん任せ。納品されたものを見て、素晴らしい色合いに会心の笑みがこぼれました。
お蔭さまで、新調した法被は大好評!! よく映える色合いで、着て貰った世話役さんにも、お寺さん方にもお褒めの言葉をたくさん頂きました。これからは、寺行事で総代さん方に被着して頂くことになります。
尚、今回の制作に当り、鈴木法衣店の登丸さんに多大なご協力を頂きました。お蔭さまで、素晴らしい法被が出来上がりました。この場をお借りして、篤く御礼申し上げます。
写真1: 門前で集合写真
法被を着ているのが、世話役の方々。礼服の方は、総代OBです。
写真2: 法被の後姿
金棒役を後から撮影。お顔も紹介したかったのですが、あしからず…。
開白法要からはや半月。今回は、そのこぼれ話を紹介します。
開白法要にて、常福寺境内に荘厳された大きな角塔婆(かくとうば)。幅七寸・長さ二間半の立派な姿は、お参りされた方の関心を強く集めました。
 そもそも塔婆とは、ほとけさまを供養する塔のことです。梵語stupa(ストゥーパ)の音訳が卒塔婆(そとば)であり、塔婆はその略語。私たちがよく目にするお墓の塔婆や、お寺にある三重塔や五重塔も、全て同じ性質のものです。
そもそも塔婆とは、ほとけさまを供養する塔のことです。梵語stupa(ストゥーパ)の音訳が卒塔婆(そとば)であり、塔婆はその略語。私たちがよく目にするお墓の塔婆や、お寺にある三重塔や五重塔も、全て同じ性質のものです。
今回荘厳された角塔婆は、落慶などの大きな法要でよく目にする機会があります。
これだけの大きさですから、書くのも建てるのもそう簡単にはいきません。大きな組織になると必ずおられるのが、筆を執る専門の方。右筆(ゆうひつ)とも呼ばれるその存在。伊賀四国霊場会では、第82番 観音寺住職 飯田辨匡(べんきょう)師がそれに当り、普段は主に会計業務を担当されています。
 開白法要より一週間ほど前、飯田師が筆墨持参でお越しになり、大きな角塔婆にすらすらと字を入れていかれます。もちろん書く内容は先に決めてあり、四面全てに所定の文字が入ります。
開白法要より一週間ほど前、飯田師が筆墨持参でお越しになり、大きな角塔婆にすらすらと字を入れていかれます。もちろん書く内容は先に決めてあり、四面全てに所定の文字が入ります。
写真は、飯田師の執筆姿と、書かれた字を乾かすうちの住職。お手伝いする私がほとんど入る余地がないほど、素晴らしい連繋でした。
 筆入れされた角塔婆は、さらしを巻いて大切に保管。そして開白前日に建立されました。
筆入れされた角塔婆は、さらしを巻いて大切に保管。そして開白前日に建立されました。
写真を見て頂いて分かる通り、大人が5,6人掛かっても運ぶだけで精一杯。
 深めに穴を掘っておいて、重機を使って建てていきます。
深めに穴を掘っておいて、重機を使って建てていきます。
昔はどうやって立てたのでしょうね。人力ではかなりの人手がいりますし、建てた頃には傷だらけになりそう。牛馬やてこの力を借りたりしたのでしょうか。
最後に、足元の土を固めます。白木の時は立派すぎないかと心配しましたが、立ててみると本堂ともよく似合います。
こうして大勢の方のご協力によって、立派な角塔婆が、開白方法に荘厳されました。塔婆一つだけでもこうですから、今回の開白法要には、本当に数えきれないほどの「お蔭さま」があった訳です。それら全てに感謝しつつ、一例を紹介いたしました。
開白法要にて、常福寺境内に荘厳された大きな角塔婆(かくとうば)。幅七寸・長さ二間半の立派な姿は、お参りされた方の関心を強く集めました。
今回荘厳された角塔婆は、落慶などの大きな法要でよく目にする機会があります。
これだけの大きさですから、書くのも建てるのもそう簡単にはいきません。大きな組織になると必ずおられるのが、筆を執る専門の方。右筆(ゆうひつ)とも呼ばれるその存在。伊賀四国霊場会では、第82番 観音寺住職 飯田辨匡(べんきょう)師がそれに当り、普段は主に会計業務を担当されています。
写真は、飯田師の執筆姿と、書かれた字を乾かすうちの住職。お手伝いする私がほとんど入る余地がないほど、素晴らしい連繋でした。
写真を見て頂いて分かる通り、大人が5,6人掛かっても運ぶだけで精一杯。
昔はどうやって立てたのでしょうね。人力ではかなりの人手がいりますし、建てた頃には傷だらけになりそう。牛馬やてこの力を借りたりしたのでしょうか。
最後に、足元の土を固めます。白木の時は立派すぎないかと心配しましたが、立ててみると本堂ともよく似合います。
こうして大勢の方のご協力によって、立派な角塔婆が、開白方法に荘厳されました。塔婆一つだけでもこうですから、今回の開白法要には、本当に数えきれないほどの「お蔭さま」があった訳です。それら全てに感謝しつつ、一例を紹介いたしました。
4月3日、伊賀四国八十八ヶ所霊場 開創150周年開白法要が、常福寺を会場に厳修されました。
当日は、寒が戻りつつも晴天に恵まれ、伊賀一円から札所寺院のご住職方、各寺院の檀信徒を併せて、600名以上のご参詣を頂きました。


内容は、法話、お練り、稚児加持、塔婆加持、堂内法要、式典、柴燈護摩、もち配りなどなど…。霊場会ブログに詳しく執筆しましたので、興味のある方はこちらをご覧くださるよく分かると思います。
開白法要について詳しく知りたい方は…、コチラ
当日の様子を、写真付きで紹介しています。
 当日は、霊場会会長であるうちの住職が、大導師という一番大切な役目を勤めました。
当日は、霊場会会長であるうちの住職が、大導師という一番大切な役目を勤めました。
霊場開創一世紀半を経て、発祥の地であるこの常福寺で150周年の開白法要が営まれたことは、誠にありがたい仏縁であります。
ちなみに私は、承仕(じょうじ)という主に下作業の役目を勤めました。本来は若手の役なのですが、法要の流れを全て理解して、先んじて行動しないといけない大切な仕事。法要の間は、ずっとバタバタ慌しく動いていました。
今回は、法要当日よりも先立っての準備が大変でしたね(^-^;A
先のブログ「てんやわんや」にも書きましたが、会場寺院ということで色んな準備をさせて頂き、どれも大変勉強になりました。また時間があれば、ブログでこぼれ話を出来ればいいなと思います。
当日は、寒が戻りつつも晴天に恵まれ、伊賀一円から札所寺院のご住職方、各寺院の檀信徒を併せて、600名以上のご参詣を頂きました。
内容は、法話、お練り、稚児加持、塔婆加持、堂内法要、式典、柴燈護摩、もち配りなどなど…。霊場会ブログに詳しく執筆しましたので、興味のある方はこちらをご覧くださるよく分かると思います。
開白法要について詳しく知りたい方は…、コチラ
当日の様子を、写真付きで紹介しています。
霊場開創一世紀半を経て、発祥の地であるこの常福寺で150周年の開白法要が営まれたことは、誠にありがたい仏縁であります。
ちなみに私は、承仕(じょうじ)という主に下作業の役目を勤めました。本来は若手の役なのですが、法要の流れを全て理解して、先んじて行動しないといけない大切な仕事。法要の間は、ずっとバタバタ慌しく動いていました。
今回は、法要当日よりも先立っての準備が大変でしたね(^-^;A
先のブログ「てんやわんや」にも書きましたが、会場寺院ということで色んな準備をさせて頂き、どれも大変勉強になりました。また時間があれば、ブログでこぼれ話を出来ればいいなと思います。
尚、当法要は、震災直後その開催の是非も検討されましたが、東日本大震災で犠牲になられた方々のご冥福を祈る追悼法要を兼ねて執行しました。
会場各所でご参詣の皆さまから義援金を募り、当日のご浄財を併せて 384,024円を、自治体を通して日本赤十字に寄付されたことをご報告いたします。
カレンダー
| 12 | 2026/01 | 02 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
最新記事
(01/15)
(01/08)
(01/31)
(01/20)
(01/15)
ブログ内検索
プロフィール
HN:
和光さん
HP:
性別:
男性
職業:
副住職
趣味:
読書、息子と遊ぶこと
自己紹介:
真言宗豊山派のお坊さん
大和国は豊山長谷寺の門前町に生を受け、仏縁あって僧侶に。
伊賀国は江寄山常福寺の副住職になりました。
現在檀務と共に、ご詠歌、声明ライブ、豊山仏青、歩き遍路など、色々活動しております。
真言宗豊山派のお坊さん
大和国は豊山長谷寺の門前町に生を受け、仏縁あって僧侶に。
伊賀国は江寄山常福寺の副住職になりました。
現在檀務と共に、ご詠歌、声明ライブ、豊山仏青、歩き遍路など、色々活動しております。
カウンター
最新TB
アーカイブ
忍者アナライズ

